育休を終えて職場に戻るのは、やっと社会復帰できる嬉しさがある反面、上手く過ごせるか不安、という方も多いのではないでしょうか。
実際のところ、保育園の送り迎えや、子どもの病気・けがへの対応など、日常はこれまでと大きく変わります。
今回この記事では、育休復帰後に直面する現実と、国の制度や職場文化を上手に活かして仕事と子育てを両立するポイントをまとめました。
育休復帰はゴールではない
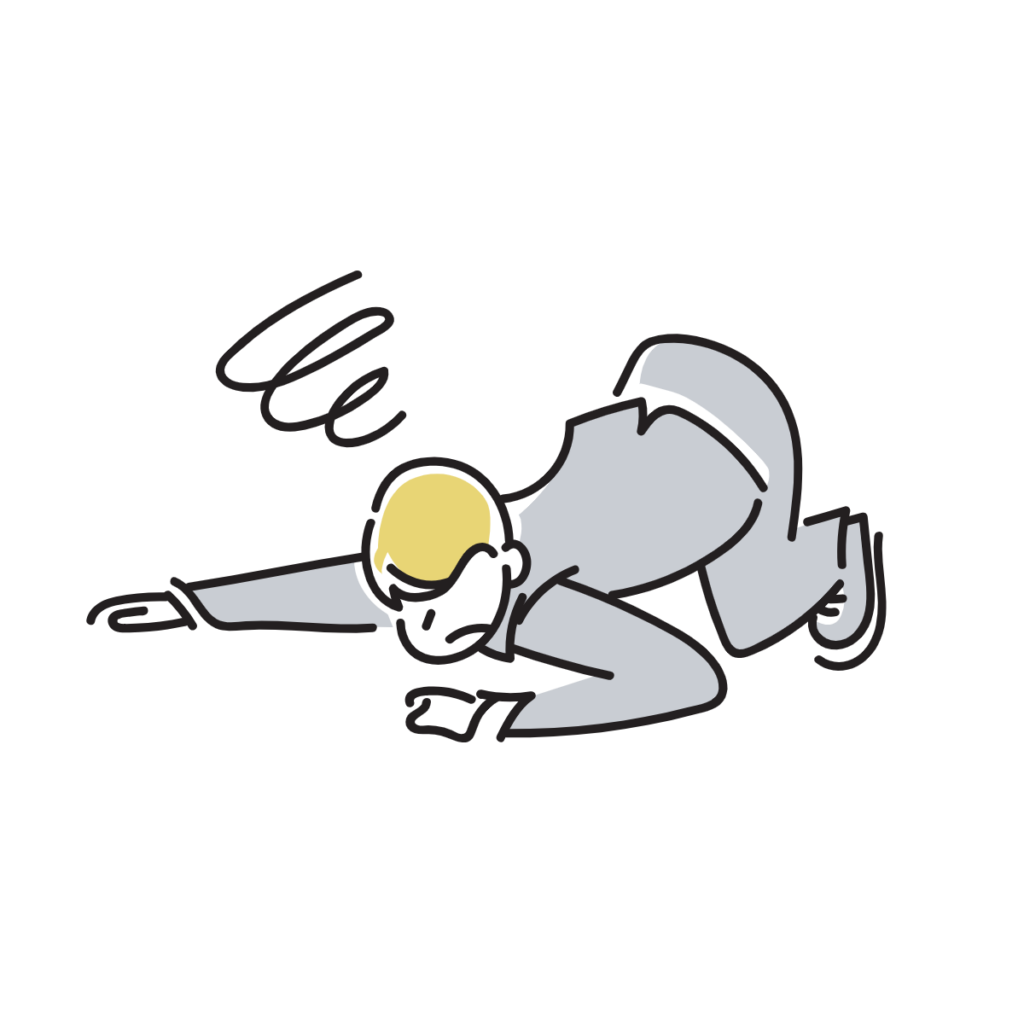
育休を終えて職場に復帰することは、ひとつの区切りでありゴールではありません。
むしろ本番は復帰してから始まります。
保育園送迎や土日や休日の相手、病気やけがの対応など、
子どもがいる生活はこれまでと大きく異なります。
多くの親が育休明けに直面するのは、保育園への入園や、慣らし保育ですよね。
希望通り入園できるかは最初のハードルで、入園できても短時間からのスタート。
特に最初の数週間は長くても3時間程度しか預けられないのです。
さらに、子どもはまだ体力や免疫力が未熟なため、病気やけがで呼び出されることもしばしば。
そのたびに早退や欠勤が必要になるため、「育休復帰=元の働き方に戻る」とは言えないのです。
復帰後は子どもがいる生活を前提に、新しい働き方を設計していく必要があります。
この現実は、特にママだけでなくパパにとっても同じはず。
それでも、育休を経て職場に戻りたいと考える人は多く、仕事にやりがいを感じながら子育ても大切にしたいという思いは、誰しも持っているものではないでしょうか。
働く親を支える国の制度
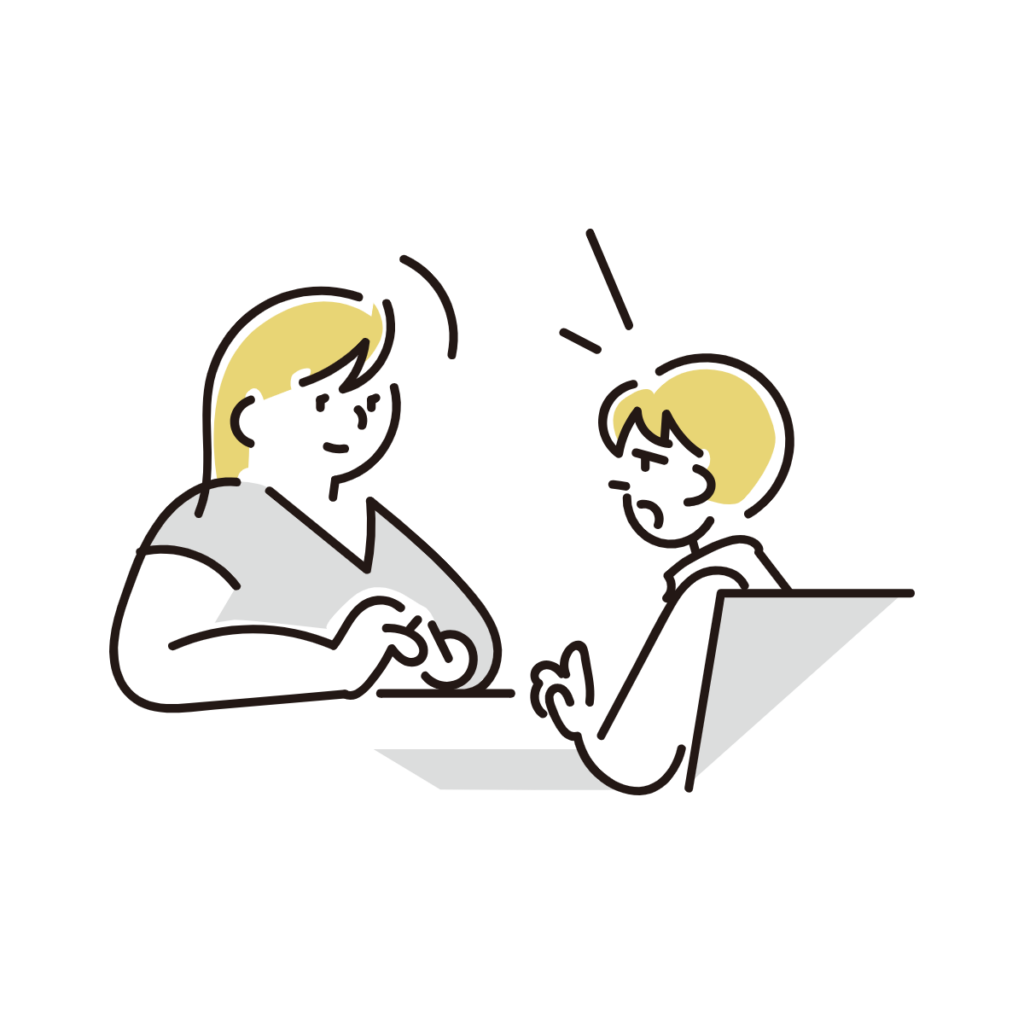
育休復帰後の働き方を支えるために、日本では法律で守られた制度があります。
これらは「育児・介護休業法」に基づくもので、会社員であれば基本的に誰でも利用可能です。
育児短時間勤務制度
子どもが3歳になるまで、1日6時間の短時間勤務を請求できる制度です。
企業は原則として拒否できません。
これにより、子どもがまだ小さい期間も無理のない勤務時間で働くことが可能になります。
子の看護休暇
小学校入学前の子どもが病気やけがをした場合や、予防接種や健診の際に取得できる休暇です。
年5日まで取得でき、子どもが2人以上の場合は年10日まで利用可能です。
急な呼び出しや病気にも対応しやすくなります。
時間外労働・深夜業の制限
小学校入学前の子どもを育てる親は、申請すれば残業や深夜勤務を免除してもらえます。
これにより、家庭と仕事のバランスをある程度保つことが可能です。
所定外労働の免除(残業免除)
3歳未満の子どもを育てている場合、残業そのものを免除してもらうよう請求できます。
業務量が多くても、法律を根拠に働き方を調整できるのは大きな助けとなります。
重要なのは制度より「文化」
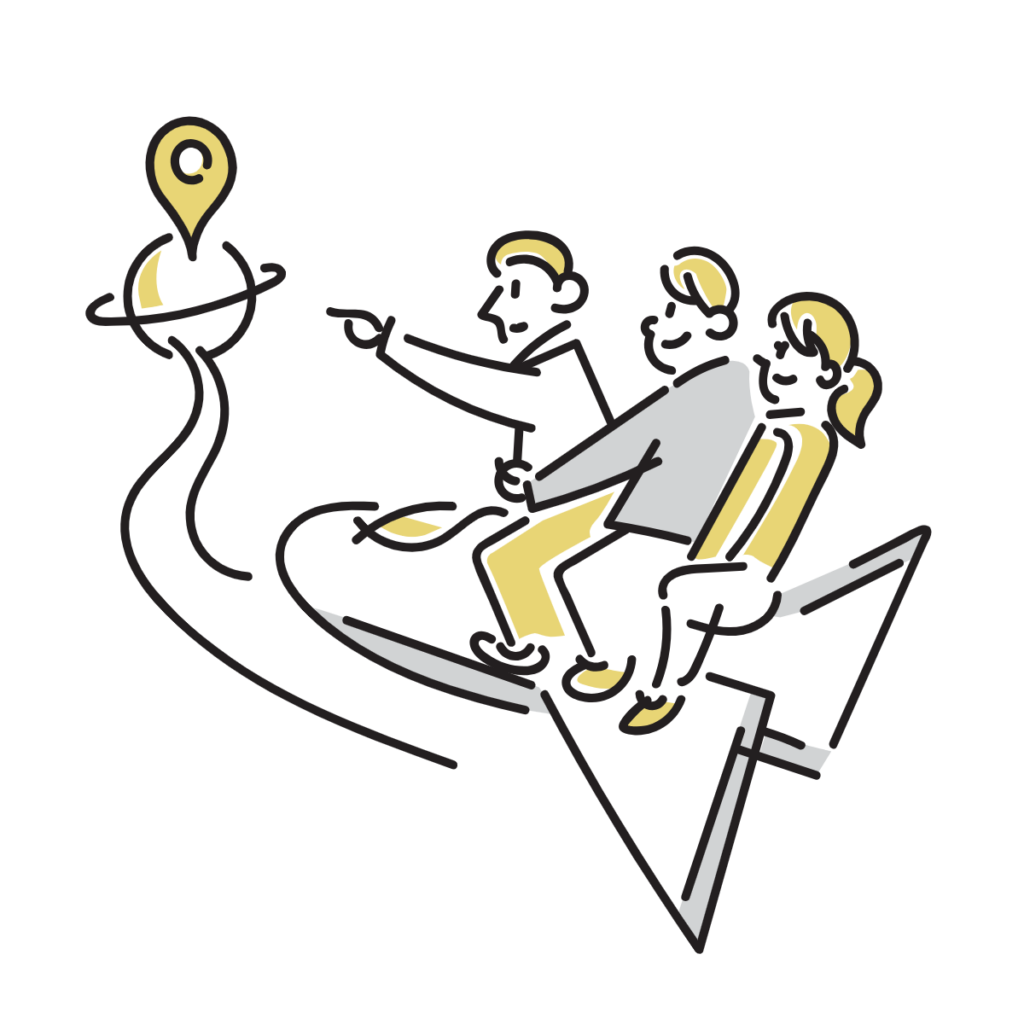
たとえ会社として制度がしっかりしていても、それだけでは十分とは言えません。
その制度が活用できるかどうかは、職場の文化や雰囲気に大きく左右されます。
「制度はあるけれど誰も使っていない」
「時短勤務とは名ばかりで、業務量は変わらない」
こういったケースも少なくありません。
制度を活用するためには、周囲との調整や時には交渉も重要なのです。
そして、「男性が働き、女性は働くのをあきらめる」という古い考え方が、
まだまだ残っている職場もありますよね。
正直に言うと、私自身が職場で「お前は働く側だろう」という空気を感じているのです。
直接言われたわけではありませんが、雰囲気として重く感じる瞬間は多々あります。
現実にはママも仕事にやりがいを感じ、復帰後も活躍したいと思う人は多いでしょう。
働く親にとって大切なのは、制度やサポートを知ること、そして周囲の理解を得ることです。
パートナー、職場、地域など、協力できる人や仕組みを活用しながら、自分の働き方を調整していくことが両立への近道になります。
自分だけで抱え込む必要はありません。
まとめ
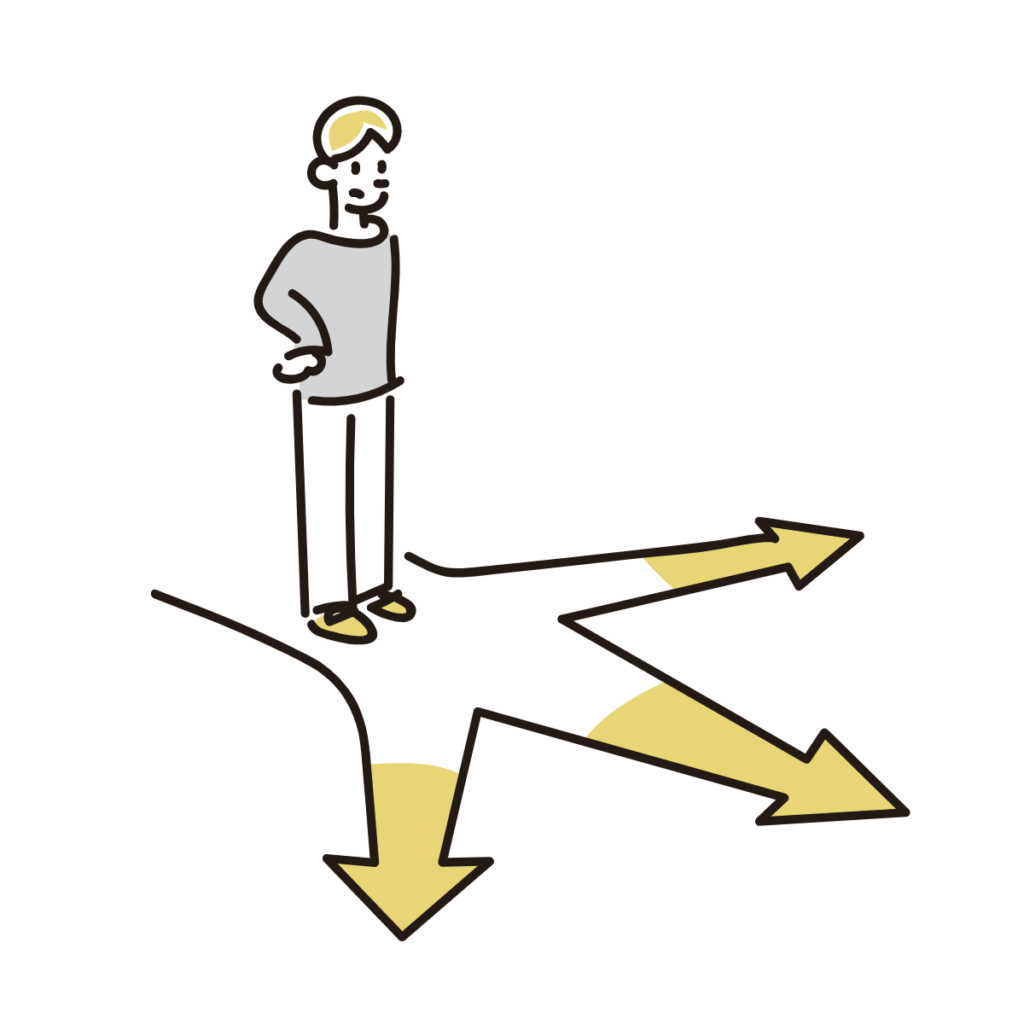
育休復帰は、これまでの働き方に戻ることではなく、新しい生活の始まりです。
国の制度を味方につけつつ、企業文化や周囲の理解を活かすことが、無理なく両立するためのポイントとなります。
「親として子育てをすること」と「人として働くことのやりがい」、どちらも諦めずに大切にできる方法は必ずあるはず。
今回は、育休復帰後に本格化する育児と働き方の両立について、国の制度を中心にまとめました。育休復帰後、仕事と子育てが両立できるか不安なパパママへ、少しでも参考になれば幸いです。
ちなみに私、こまひつじの3回目の育休は9月をもって終了します。
末娘の慣らし保育に難航している話、
私自身の今後の働き方について、悩んだ末に出した答えについては、またどこかで。
では!
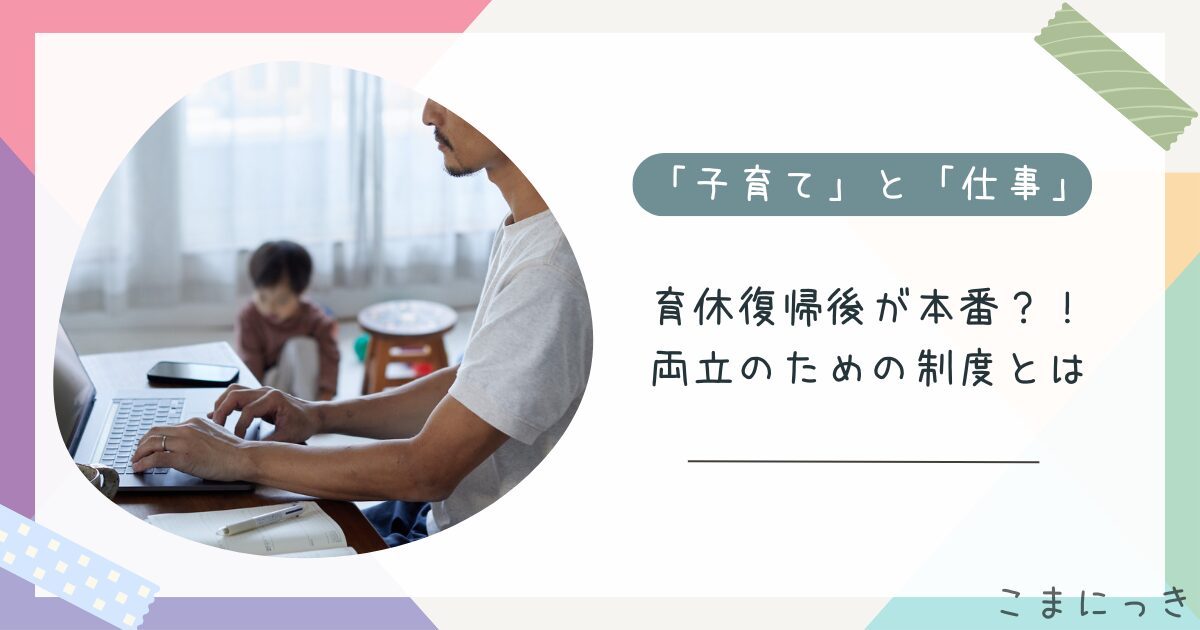


コメント