こんにちは!こまひつじです。
近年、男性の育休取得率が急激に上がっていますが、満足度は人それぞれですよね。
「やってよかった!」と感じる人もいれば、
「なんかモヤモヤ…」と後悔で終わる人もいるのでは。
そこで本記事では、成功するパパ・失敗するパパの違いをシンプルに解説します。
実体験も交えつつ、後悔しない育休にするためのヒントもお届けします。
さっそく、いきましょう!
上手くいくパパの特徴3つ

①パートナーと役割を明確にできている
育休に入る前に「目的」や「自分の役割」といったことを、
事前にパートナーと話し合っている人は良いスタートがきれます。
たとえば育休の目的が、
- 「ママの体調回復をサポートするため」なのか
- 「パパが積極的に育児スキルを身につけるため」なのか
それぞれで関わり方はかなり変わってきます。
また家事や育児の分担も、
- 「パパが基本的に家事全般を担う」のか
- 「赤ちゃんを見てる方と逆の人が家事をする」のか
ある程度具体的に決めておくことで、日々のイライラやすれ違いを減らせます。
実際は、生まれてからバタバタするし、予定通りにいかないことも多いです。
それでも、土台となる方針を決めておくことが、スムーズなスタートにつながります。
②「自分事」として関われている
育休をサポートではなく、「自分の役割」だと捉えられるかどうか。
ここが、育休をうまく活かせるかどうかの分かれ道です。
「手伝うよ」「何かあったら言ってね」というスタンスは、どこか他人事。
洗濯も食事もおむつ替えも、「自分がやるのが当然」という前提に立てるかどうか。
主体的に関わることが、育児への自信にもつながり、
育休を「取ってよかった」と思える大きな要素になります。
③育休中の過ごし方に「目標」を設定する
育休を「ミッション」と捉え、
小さな目標をもって過ごせるパパは満足度が高くなると感じます。
もちろんお世話そのものは楽しい時間ですが、
それだけではモチベーションも保ちにくくなることも。
例えば…
- 赤ちゃんと2人だけで外出できるようになる
- ママが1日外出しても問題なく過ごせる
- 予防接種は自分が連れていく
といった具体的な目標を持つだけでも、行動の方向性は定まりやすくなります。
さらに、「赤ちゃんと2人で出かける」目標を達成するために…
- 「オムツは基本、毎回変える」
- 「抱っこヒモに慣れておく」
- 「お散歩の準備は自分がやる(何が必要か覚える)」
といった小さなステップを積み重ねていくのも、
達成感が生まれ前向き気持ちで過ごすことが出来ます。
挫折するパパの特徴3つ
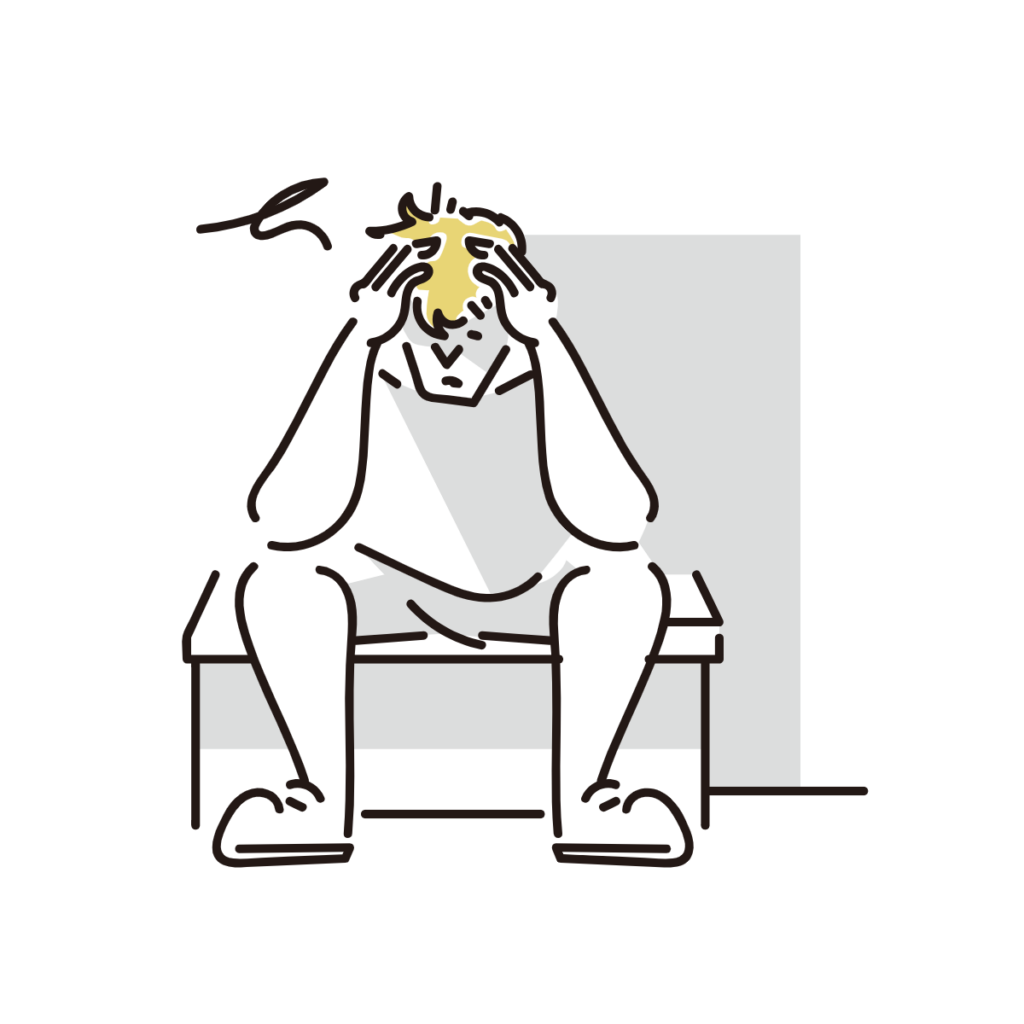
1)なんとなく育休を取ってしまった
育休を取ったものの、何をすればいいか分からず、ただ時間を持て余すだけに。
準備不足のまま新生児期に突入すると、ママに頼りっぱなしになり、
うまくできずに気まずさが募り、育児への苦手意識が芽生えてしまうことも…
「育休中に何をしたいか?」をざっくりでも事前に考えておくと、
迷いなくスタートが切れます。
2)関わり方が「サポートどまり」になっている
「言ってくれたらやるよ」では、育休中の信頼は築けません。
いちいち説明しないと動かない状態ではママの負担は減らず、
むしろストレスが増してしまいます。
『他人事』のままでは、お荷物扱いされてしまうことも。
まずは「自分から気づいて動く」こと。
小さな家事や育児を、自発的にやってみるだけでも大きく変わります。
3)夫婦での対話が不足している
「言わなくてもわかるだろう」では、すれ違いが生まれやすくなります。
育児中は心の余裕がなくなりがちなので、察するよりも伝え合うことが大切。
話せない日々が続くと、気づけばお互いに不満が溜まり、ギスギスしてしまう原因に。
一日一言でも「どうだった?」と声をかけ合うだけで、空気はガラッと変わります。
せっかくとった育休、後悔しないために!
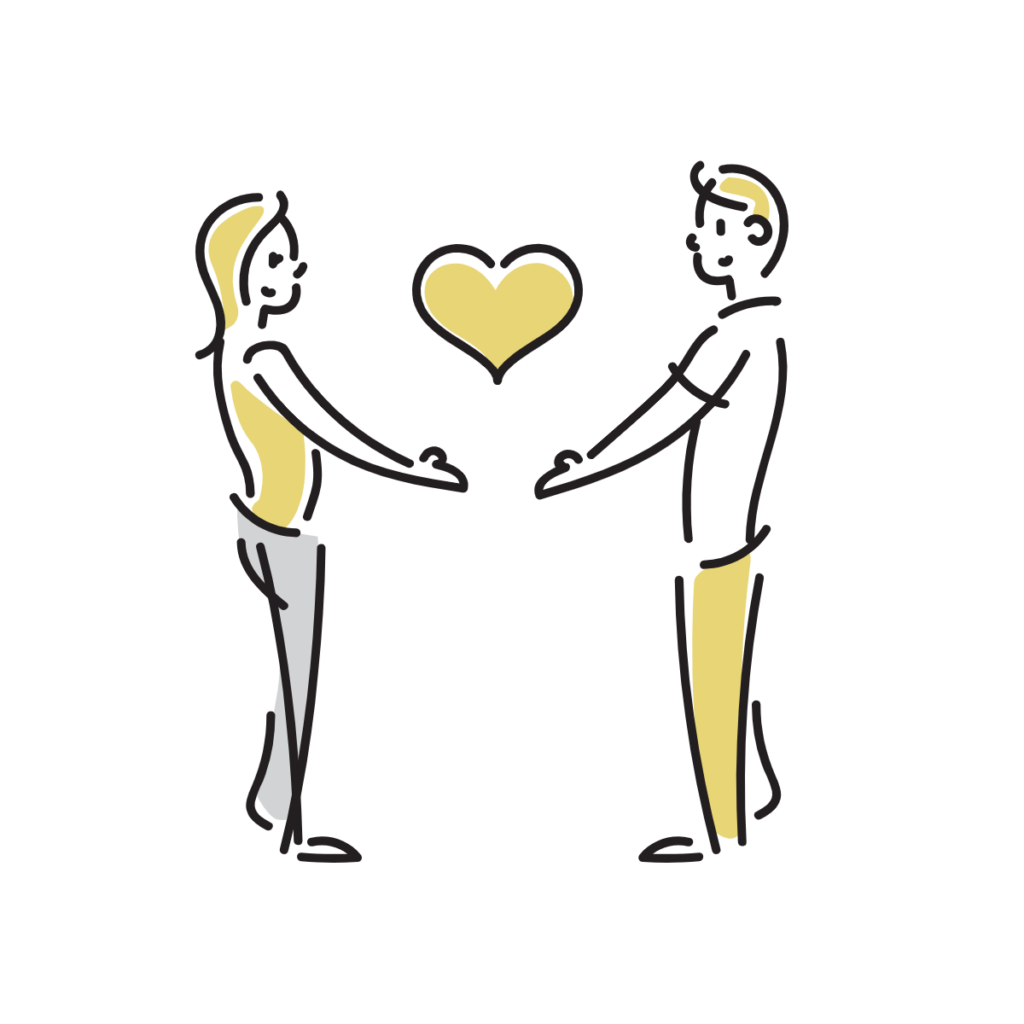
せっかく手にした育児休業です。少しでも無駄にしたくないですよね。
でも人間は不思議なもので、時間があるとついボンヤリ過ごしてしまいがち。
だからこそ、意識しておきたいポイントは次の通り。
- 育休前に最低1回、夫婦で話し合う時間を設ける
- その際、「何をするか」「どこまでやるか」をきっちり言語化する
- 理想の育休像はざっくりでいいので共有しておく
- 完璧を目指さず、変化に対応できる柔軟さも大事
- 時間があるなら、復職後のこともちょっと考えておく
赤ちゃんの成長スピードは驚くほど早くて、
先週出来なかったことが、いつのまにか出来ていたりします。
そんな瞬間を見逃さないように、前もって準備して臨みましょう。
まとめ:育休は取ることがゴールではない。
ここまで、育休が成功するパパと、失敗してしまうパパについて考えてきました。
育休の成功・失敗を分けるのは、『どう過ごすのか』です。
主体的に関わり、夫婦で対話を重ねることが何より大切。
育児休業を取得する理由や背景、期間などは千差万別ですが、
どんな形であれ、「取ってよかった」と思える育休になりますように。
そう願っています。
では、また次回の記事で!
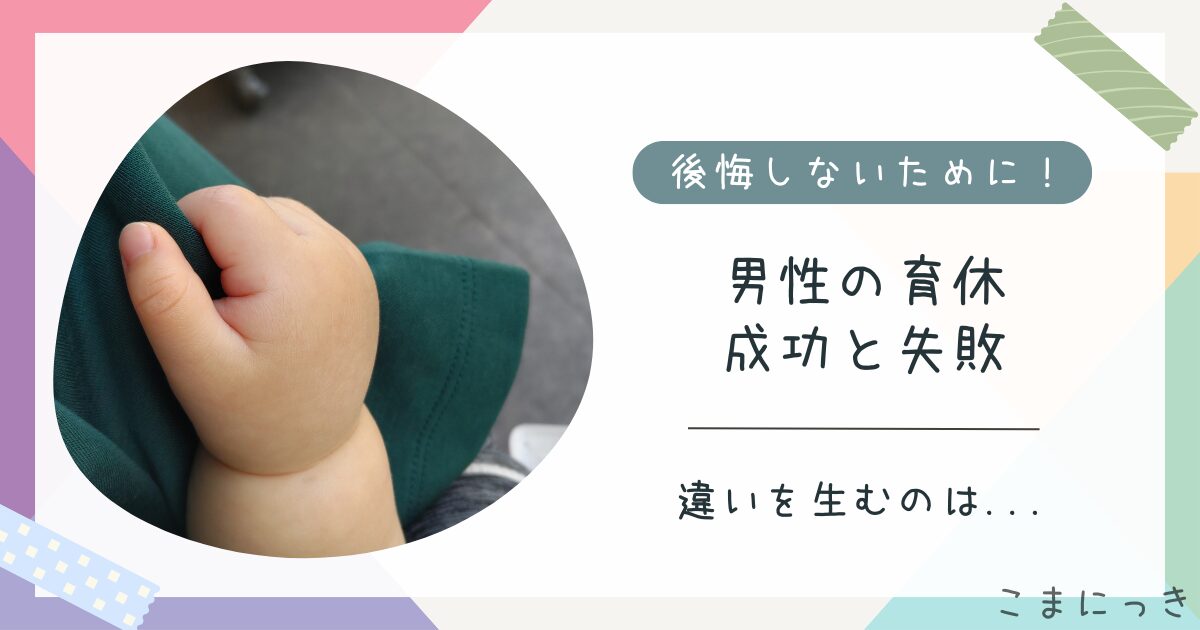


コメント